年収の節目である「~万円の壁」と呼ばれている「壁」がそれぞれ一体何を意味するのか?と思うことありませんか?
そして、2024年10月には法改定も決まっています。
扶養から抜ければ、保険料が引かれる分手取りは減ります。そこで、
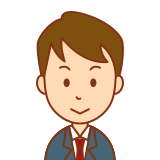
よく「106万の壁」とか「130万の壁」とか
聞くけど何のこと?
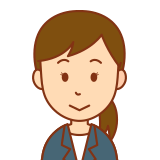
そもそも「扶養」とは、
どういうことなの?
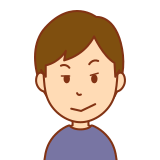
75歳以上の人は扶養できないの?
など『扶養』や『〇〇の壁』について、よくわからないとゆう人に向けて、疑問や悩みをFPの私が解消します。
この記事を最後まで読んで頂くことで、
②「扶養から外れる」ってどういうことか
③「103万の壁」とは何か
④「106万の壁」とは?
⑤「130万の壁」とは?
⑥その他の壁
⑦後期高齢者医療制度と扶養について
が解るようになります。
なお、本ページはプロモーションが含まれています。
『扶養』について
『扶養』には、2つの種類があります。
それが、
「社会保険上の扶養」
です。
ということで、まずは「扶養」を理解しましょう。
では、順番に
②「扶養から外れる」ってどういうこと?
について説明し、次に「壁」とは何かを見ていきましょう。
そもそも『扶養』とは?
『扶養』とは、一般的に、
「自分の生活を自分で維持することができない者に対して、その生活を援助するため何らかの給付を行うこと」をいいます。
夫の所得が1,000万円以下の場合、パートで働く妻を扶養に入れることで夫の所得税と住民税を減らすことができる「配偶者控除」と「配偶者特別控除」という所得控除のことです。
つまり、簡単に言いますと、本来支払わなければならない「所得税や住民税の一部」が免除(控除)されるのです。
所得税法では、扶養される方の給与収入額の上限は「103万円」と定められています。
我が家の場合、OLだった妻は私と結婚したことで私の扶養者となり、「扶養手当」が支給されるし、「健康保険」などの掛け金も支払わなくてよくなりました。
これが「扶養内」の状態、つまり、
「103万の壁」を超えていない状態ですね。
パートなどの給与収入が「103万円」を超えたとしても150万円以下であれば配偶者特別控除が満額適用でき扶養からは外れません!
ただし、150万円を超えて稼ぐとこの配偶者特別控除の額が徐々に減り、年収201万円を超えると控除がなくなります。
これが、「税法上の扶養」のことです。
「扶養から外れる」ってどういうこと?
「扶養から外れる」ということは、一般的には、『社会保険』を自分で支払うことを意味します。
つまり、『社会保険』の扶養内の人は、自分で保険料を支払うこと無く、健康保険に加入することができるのですが、扶養から外れると自分で社会保険料を支払うことになります。
冒頭で言いましたが、これがもう一つの「社会保険上の扶養」のことです。
ちなみに、『社会保険』とは、
「健康保険」や「厚生年金保険」の総称となります。
なお、
「健康保険」や「厚生年金保険」については別に書いていますので、どうぞご参考にしてください。
⇒『「健康保険」について知りたい!【種類・加入・保険料】はどうなっているのか?』
⇒『国民年金と厚生年金の制度の違いや支払いはどうなっているのか?』
「106万の壁」とは?【注意すべき点】
いわゆる「106万円の壁」と「130万円の壁」が『社会保険の壁』と呼ばれます。
「106万円の壁」というのは、一定の要件を満たし、「年収106万円を超えると扶養から外れ社会保険に加入が必要だ」という年収の目安として使われる言葉です。
2022年10月までは、
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・従業員500人を超える勤務先で働く
などの条件を満たすパートやアルバイトの人は、年収106万円以上になった時点で、自ら健康保険・厚生年金などの社会保険に加入することになっていました。
しかし、2022年10月からは、以下の2つが変更となりました。
→101人以上の企業に変更
②雇用期間の見込みが1年以上
→2ヵ月以上へと変更
さらに、2024年(令和6年)10月からは、
従業員数が51人以上の企業も対象となる予定になっていること。ますます、社会保険に加入するパートやアルバイトの人が拡大されることになります。
さて、「106万円の壁」のポイントは、
あくまでも月額賃金の88,000円を基準として、「自分は社会保険への加入条件に当てはまるかどうか?」が判断する目安になります。
社会保険料がかかる人の条件は、以下のとおりです。
✅賃金が月額8.8万円以上
✅雇用期間の見込みが2ヶ月以上
✅学生ではない
✅事業所の従業員数が101人以上
ひとつでも条件を満たさない場合には、社会保険の加入義務はなく、保険料もかかりません。
現在政府は、パート労働者らに社会保険料負担が生じる「106万円の壁」への方針として、労働時間を延ばしたり、賃上げしたりした企業に助成金を出すとしています。
注意して欲しいことは、今までは大丈夫でも、2024年10月からは、企業の規模や雇用期間が変わります。
勤務先の従業員が51人のために、健康保険と厚生年金への加入対象になることがあるという点です。
なお、この金額には、賞与や報奨金、精皆勤手当などの一時的な収入も月額賃金には含まれません。
「130万の壁」とは?
『130万円』!
それは、
「社会保険の扶養」とするための給与収入の限度額を指しています。
今までは、たとえ、月額賃金が88,000円以上でも、2ヶ月未満の雇用契約や、週に20時間未満の労働などの加入条件にあてはまらない場合は、130万円までは扶養範囲内で、社会保険への加入は必要ありませんでした。
しかし、106万円の壁に該当しなかった人でも、年収が130万円を超えると、全ての人が社会保険の扶養から外れ、社会保険の加入対象となるのです。
パート労働者の中には、
「働く時間を調整して少なくしているが、他の人が休むと自分が出ることもある。今年は、130万円を超えているのでは?と思うこともある。現状は働きたいけど、勤務時間を減らさなければならない。」
と、本当はもっと稼ぎたくても、働く時間を減らさざるを得ないという矛盾が日常的に生まれています。
このため政府の方針として、
130万円を超えたパート労働者らについて、「連続して2年までなら扶養にとどまれるようにする」としています。
なお、算定される報酬月額には、
基本給のほか、残業代や交通費、住宅手当や家族手当等の諸手当が含まれます。
エピソード
私が公務員でいた時の思い出話です。
友人の公務員の奥様はパートで働いていました。
とうぜん、収入が年額130万円を超えたら扶養から抜けてしまうこともご存じでしたので、月に10万円以上にならないよう気をつけていました。
12月に奥様のパート仲間が体調不良のため、その数日間も奥様が臨時で働くことになったのです。
その後、店長さんは、
「頑張ってくれたので、給料の他にちょっとだけとボーナスを出すよ。」
ということで、給料と合わせてその月は15万円となり、旦那様も奥様も大喜び!
さて、
公務員の扶養認定条件の中に、
という内容があり「3か月間」を基準としています。
つまり、
3ヶ月の月平均が108,333円を超えた時期があり、扶養取消となったのです。
今回の場合は、
10月 10万
11月 10万
12月 15万
合計 35万円
3ヶ月で割ってみますと、116,666円!
なんと、108,333円を超えています。
このように、
扶養認定条件によって扶養を外れる場合があるので注意しましょう!
その他の「壁」
配偶者控除と配偶者特別控除の満額は、同じ38万円です。
「103万円の壁」の他にも、「150万円の壁」や「210万円の壁」という『税法上の壁』がありますので、簡単に触れておきます。
「103万の壁」について
『103万円の壁』!
これは、
「税法上の扶養」とするための給与収入の限度額を指しています。
前述しましたとおり、
扶養される方の給与収入が103万円以下であれば所得税の扶養に入ることができます。
ここで注意すべきポイントは、
この給与収入には所得税法上非課税となるもの、例えば、「通勤手当」は含まれませんので、除外されます。
また、残業手当や休日出勤手当、賞与、結婚祝い金などの臨時に支払われるものは含まれません。
『150万円の壁』
年収150万円を超えて稼ぐと、
配偶者は、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の額が徐々に減ります。
『201万円の壁』
年収201万円を超えると、
配偶者は、「控除」がなくなります。
小まとめ
ここまで、
「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」及び「壁」について説明しました。
超簡単にポイントをまとめますと
・所得税の扶養は、201万円まで!
と覚えておくのがいいですね。
後期高齢者医療制度と扶養について
扶養していた方が75歳になると「後期高齢者医療制度」の適用者となります。
そのため、
社会保険や健康保険上の扶養に入ることはできなくなります。
もし、扶養していた方(例えばお母さま)が75歳になったら、扶養から外れるということでしょうか?
という疑問が出ると思います。
そこで、簡単に「後期高齢者医療制度」と「扶養控除」について説明して、次にそれらの関係を見ていきましょう。
「後期高齢者医療制度」とは、
健康保険の被扶養者となっていた方が、75歳になると自動的に健康保険の被扶養者から外れ、「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
被扶養者になれば、今までは自分で「保険料の負担」をしなくともよかったのに、その後は、
ご自身で保険料を負担することになります。
「扶養控除」について
「所得税の扶養控除」の対象となるのは、年間所得金額が38万円以下の場合です。
給与や年金は、一定の控除額がありますので、
・年金収入の場合には、年間158万円以下
であれば、年間所得が38万円以下となり、扶養控除の対象となります。
「後期高齢者医療制度」と「扶養控除」の関係
さて、「後期高齢者医療制度の被保険者」となり、「社会保険の扶養から外れた場合」ですが、所得税を計算する際の扶養控除には、一切影響がありません!
なぜなら、所得税は、
所得が38万円以下であることが基準ですから、社会保険の取り扱いに変更があっても、年金収入が年間158万円以下であれば「扶養控除」が適用できるのです。
つまり、「節税」になります。
ただし、じっとしていても解決はされません!
将来の年金やライフプランなどの不安がある方は、プロに相談してみるのはいかがでしょうか?
【無料】ですから安心ですね。
『扶養』のまとめ
今回は、
『【扶養】2024年10月から注意すべき「106万円の壁」!』
と題しまして、
・よく「103万の壁」とか「130万の壁」とか聞くけど何のこと?
・そもそも「扶養」とはどういうことなの?
・75歳以上の人は扶養できないの?
などの疑問を持っている方に向けて、
②「扶養から外れる」ってどういうことか
③「103万の壁」とは何か
④「106万の壁」とは?
⑤「130万の壁」とは?
⑥その他の壁
⑦後期高齢者医療制度と扶養について
が解るように説明しました。
ポイントは、「扶養」には、
「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの種類がありました。
特に今回のポイントは、
「106万円の壁」でした。
2024年10月からは、従業員数が501人以上の企業→51人以上の企業に変更となります。
そのため、注意して欲しいことは、
今までは大丈夫でも、勤務先の従業員が51人のために健康保険と厚生年金への加入対象になるということがあるという点を説明しました。


